10月 14th, 2009 by taso


監督・脚本:森田芳光
製作・企画:鈴木光
プロデューサー:青木勝彦、三沢和子
キャスト:深津絵里、内野聖陽、戸田菜穂、宮沢和史ほか
主題歌:『TOKYO LOVE』:THE BOOM
1996年/118分/カラー/日本
画像クリックでAmazon詳細ページ
チャットの様子が画面いっぱいに映し出されたり、電光掲示板の文字が挿入されたり。そんな文字の演出はどこかアナログ感が漂っていて、インターネット黎明期の感覚を懐かしく思い出させる。
『(ハル)』が公開された1996年は、インターネットがこれから普及しようとしていた時代だった。当時は目の前のキーボードで打った文字を送信することも、それを誰かが受信することも、いまいち理解できない不思議な現象だった気がする。
“ハル”(内野聖陽)は、興味本位で覗いたパソコン通信の映画フォーラムで “ほし”(深津絵里)と出会う。ハルとほしは(おそらく大多数の人々と同じように)普通の生活を送っている男女。ハルは東京に暮らすサラリーマンで、ほしは職を転々としながら盛岡に暮らしている。
華やかでもなく金持ちでもなく、一見穏やかな暮らしをしている人にも、人の数だけ習慣があり、興味がある。そして、できれば誰かに聞いてほしいことを抱えている。ふたりは生活の出来事や悩みをメールで打ち明け合うようになっていく。
インターネットがこれほど身近になると、かつてはあった切実さが欠けてくる。目の前のディスプレイに向かって、ここに自分がいることを誰かにわかって欲しい、と切なる願いを込める機会は減ったのではないか。2009年の我々はいちいちそこまで考え込まない。思いを溜め込む前に送信ボタンや公開ボタンでそれを吐き出してしまう。
それに、姿の見えないやりとりでは、文面から相手を想像するものの、相手が実在するという実感が希薄になってしまう。(このブログを読んでくれている人の姿をうまく想像できないのと同じように)
だからハルとほしが初めてお互いの姿を確認するシーンは、緊張感に溢れている。毎日のようにメールを交換した相手が本当に実在することを遠目に確認したシーン。あまりにも控え目で、短時間の接触ではあるけれど、それは目の覚めるような感動を与えてくれる。
インターネット無くしてはかなわなかった出会いもある。ハルとほしのように。
『(ハル)』という映画は、誰かと思いを共有したいという切実さに満ちている。そして、回線に接続中の大勢の、そのうち稀有な何人かが自分のメッセージを受け取ってくれるなら、本当の思いを話したい。
ハルとほしが築いた信頼関係は、今より更にインターネットが発達するであろう未来においてまで、多分、まるで色褪せることはない。インターネットがいくら発達しようと、そもそもインターネットの有る無しや、姿の見える見えないに関わらず、人間の求めるものはきっと、ずっと変わることがない。
本日の1曲
Honeysuckle Rose / Holly Cole Trio
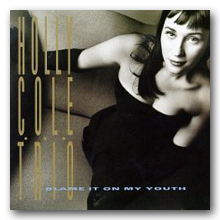

6月 5th, 2008 by taso


FREEDOMのTVCMが放映され始めたのは2006年4月。一目で大友作品と判るキャラクターと、言わずと知れたカップヌードルの組み合わせ。宇多田ヒカルの楽曲と『自由を掴め。』というシンプルなコピー。多くの人がそれぞれの理由で注目した鮮烈な幕開けだったのではないかと思う。
日清カップヌードルの知名度は高く、もはや「宣伝」の必要はない。宣伝するための広告ではなく、世界観のみを提示する広告展開はやっぱり特異だった。
特に第3話の予告編となっていたCM(YouTube)は特に印象深く、しばらく残響が持続した。
アニメーション「FREEDOM」を中心としたFREEDOM PROJECTは、二年半をかけたシリーズの完結を迎えるまで、3ヶ月ごとのDVD発売・CM放映・街頭広告・動画配信など、長期的なプロモーションを展開していった。(アニメーション本編にもカップヌードルを食べるシーンが盛り込まれ、宇多田ヒカルの楽曲の歌詞にも「カップヌードル」は登場、アニメーションをコラージュしたミュージックビデオ(YouTube)も制作された。)

作品の舞台は、23世紀の月。崩壊した地球文明を見捨てた人々は月共和国「エデン」を形成する。エデンは平穏な生活が約束された代わりに、全てを運営局に管理された自由無き場所として描かれている。
ある日、タケルは月面で一枚の写真を拾い、地球がまだ生きていることを確信する。そして写真の女の子に会うため、無謀にも危険な地球行きを決断してしまう。
第2話には、エデンを抜け出したタケルとカズマが、青い地球を目にして立ち尽くすシーンがある。それは感動的な地球との出会いであると共に、エデンによる巨大な嘘があばかれた瞬間でもある。美しい作画の中にも、自由を奪われることの恐ろしさを感じさせる名シーンではないか。
この作品を見ていると、自分の中に「タケルならこうするだろう」というプロットが無意識に組み立てられていく。そしてタケルはそれを裏切ることがない。本当の自由は、逃げることでは得られない。そんな一番真っ当で最も困難な道をタケルは選択していく。
FREEDOM SEVEN 発売記念
オールナイト上映イベント @テアトル新宿
2008年5月31日土曜日、『FREEDOM』全6話+特別編『FREEDOM SEVEN』がオールナイト上映された。
深夜0:30、本編上映に先駆けて森田監督以下制作スタッフが登場し、ステージトークが始まる。会場は立ち見を含め満員である。
まるで部室のような雰囲気の制作スタジオ(平均年齢25歳!)の様子や、DVDの発売よりCMが先に放映されるという「オチが丸分かりのジレンマ」など、息つく暇がないほど次々にエピソードが披露され、会場が沸く。
曰く、今夜は『最初で最後の上映』。朝までかけて全7話がインターバルのように上映され続けた。大音響のロケット発射シーンでは、タケル達と一緒に宇宙空間を移動しているような気になったし、描かれた宇宙空間は胸のすくようなSFへの憧憬を思い起こさせた。すべての上映が終わった時、会場に大きな拍手がおこり、監督は手をあげてそれに応えていた。
構成を担当した佐藤大氏は、普段OVA(リリースのみでテレビ放送がないアニメ作品)ばかりやっているので、今日は見た人の顔を見られるのが楽しみにしていると語った。それはこちらも同じで、製作した人の顔や、その想いを知ることができたことはとても興味深い体験だった。
本日の1曲
Kiss & Cry / 宇多田ヒカル

4月 20th, 2008 by taso
16才のアレックスははじめたばかりのスケートボードに夢中。
今日もお気に入りのスケボーパーク「パラノイドパーク」へ出かけていく。
しかし、ふとした偶然から、誤ってひとりの男性を死なせてしまう。
目撃者は誰もいない。おびえ、悩み、不安に駆られながらも、
まるで何事もなかったかのように日常生活を送っていく。
ー オフィシャルサイト〈STORY〉より一部抜粋
初めて行ったスケボーパークで、常連のスケートボーダーを眺めるアレックスの後ろ姿は格好良いものに憧れ、自分自身に退屈していたティーンエイジャーの頃を思い出させる。彼の後ろ姿に、居場所を見つけたいという切実な願いや、普通の少年の劣等感が滲んでいた。
『パラノイドパーク』の映像は、遮断された自分だけの世界を歩いているような浮遊感を感じさせる。スローモーションの映像に音楽をかぶせた演出は、緩やかなテンポの音楽をイヤホンで聴きながら街を歩いている感覚に近い。すれ違いはしても交わることのない多くの人々と、適度な孤独がもたらす安心感の類。
本作の撮影監督はウォン・カーウァイ(王 家衛)作品で独特の撮影スタイルを披露したクリストファー・ドイルが担当している。彼はカメラを「手持ちで」扱い、うねるようなカメラワークで対象を撮影する。
流れる景色にスローな音が重なる、そんな物事との距離を象徴するような映像演出は、少年の心情にとても近いように感じられた。
図らずも殺人を犯してしまった主人公アレックスも、事件が起きるまでは普通の少年だった。無邪気な仲間達と変わりない日常を送っていたはずなのだ。しかし事件の顛末を知ったその日から、全く違う次元にある世界の存在に気づいてしまう。
作品のストーリーは、随分前に見た悪い夢のようだった。夢の中で夕飯を食べながら楽しく談笑していると騒々しく玄関のドアが開き、ある友人が駆け込んできた。そして彼はたった今、人を殺してしまったと言った。殺すつもりはなかったがなぜかそこにいた老人を殺害してしまったと。彼は魂が抜け落ちてしまったみたいに生気がなく、思考が停止した空っぽの目をしていた。
日常に突然割って入った事件が、その場にいた偶然を激しく後悔させた。
___ なぜ、今晩ここに来てしまったんだろう?
___ なぜ、こんな事件を知る羽目になってしまったんだろう?
その夢はとてもリアルだったから、それが夢であったことに深く安堵した。しかし本当の恐怖の種類を知った気がして、目覚めたあとも暫く胸騒ぎが治まらなかった。
『パラノイドパーク』は誤って人を死なせてしてしまった16才の少年の、これからも続く人生の一部を描いたに過ぎない。彼は誰にも真相を打ち明けずに、このまま生きていくことが出来るのだろうか。
少年が殺人を犯してしまうというあらすじは、この作品のポスターにさえ印字されている。言うなれば、それだけの映画なのだ。
しかしあらすじを知ってしまっても、この映像は観るに値する。きっと、あらすじなんてこの作品のほんの、ほんの一部でしかないのだと思った。
本日の1曲
Oram / Fridge

——————————-

▼『
パラノイドパーク 』【予告編】
監督・脚本:ガス・ヴァン・サント
撮影監督:クリストファー・ドイル
原作:ブレイク・ネルソン
2007年/85分/カラー/アメリカ・フランス
2008年4月12日(土) シネセゾン渋谷他にて全国順次ロードショー
2月 23rd, 2008 by taso
アニー・リーボヴィッツとの撮影を終えたわずか数時間後にジョン・レノンは暗殺され、その写真は広く世に知られることになった。胎児のように体を丸め、全裸でヨーコに抱き着く彼のポートレイトを見ていると、そんな皮肉な運命が信じられなくなる。
『アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生』は、女流写真家アニー・リーボヴィッツの半生を描いたドキュメンタリームービーである。ハリウッドスターや世界有数のモード誌の編集長、あのヒラリー・クリントンまでが登場し、アニー自身とアニーの作品の魅力を興奮した表情で話す。
かの有名なRolling Stone誌にカメラマンとして在籍していた間、アニーはロックバンドのツアーに同行し、ステージ写真のほか、バックステージや滞在先のホテルなどでオフショットを撮るようになる。
日常的な風景と人物との間にも、思わず記録せずにはいられない瞬間がやってくる時がある。多くの人はレンズを向けられたその瞬間に他者を意識してしまう。あるロックスターは「(行動を共にしてから数日後には)彼女の存在が気にならなくなった」と語った。
それはカメラのレンズを介した両者がイコールに近いエネルギーを発する時に起こりうる現象で、エネルギーが多くても少なくても、それは叶わない気がする。たとえ優れた表現者を前にしても、彼女にはレンズの向こうの被写体とイコールになれるエネルギーがある。だからこそ存在を「消す」ことができたのではないだろうか、と。

__ 個性的で表情豊かなモチーフが目の前に用意されていたら、シャッターを切りさえすれば印象的な写真が撮れる? それなら誰がシャッターを切っても同じだということにならない?
以前ある友人氏は不思議そうに言った。
確かにフォトジェニックな(絵になる)モチーフや人物は写真を魅力的なものにする。しかし写真は一人の人間の限られた視界そのものであり、一枚の写真にはそこに存在することを選択した個人の意思が反映されているはずなのだ。写真を見るとき、その対象にレンズを向けた人間のアイデンティティを感じないだろうか。同じ場所に立っても同じ視界を持つ人間はいないはずで、瞬間を記録したい衝動がシャッターボタンを押させるのだから。
アニーは幼い頃から転居の多い生活をしていたみたいだった。景色を眺めながら次の土地へ向かう彼女にとって、車の窓枠は世界を切り取る「フレーム」だった。車を運転しながらインタビューに答えるアニーは、『私はいつも写真の構図のことばかり考えている』と言った。
確かに、毎日デッサンばかり描いていた浪人生の頃は、どこにいて何をしていても、物質の光の反射や、影や、パースペクティブが気になって仕方がなかった。親指と人差し指で作ったLの字を目の前にかざし、視界をトリミングしたりもした。
それはおそらく、「表現者の目」を持っているがゆえの癖のようなものだ。表現者は常に見つめ続けている。何かを表現するためには、物事を見つめなくてはならない。しかし表現者でなくなってしまえば、その癖もいつしか消えてしまう。
髪を振り乱しながらポートレイトを撮影するアニーの姿は喜びに溢れ、野性を感じさせもした。
映画館を出ると、久し振りにモノクロのポートレイトを撮りたくなった。それと同時に、今の自分は何に愛を感じてシャッターを切れるのだろうかとぼんやり考えもした。
本日の1曲
Simple Song / Richard Ashcroft

——————————-
▼『アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生』
http://annie.gyao.jp/

監督・製作:バーバラ・リーボヴィッツ
2007年/83分/カラー/アメリカ
Photographsc2007 by Annie Leibovitz
2008年2月16日(土)より シネマGAGA!、
シネカノン有楽町2丁目他 全国順次ロードショー
9月 23rd, 2007 by taso
 この映画の存在を知った当初真っ先に沸いたのは、なぜフィンランド?という疑問だった。しかし作品を観ているうちに、その答えらしきものをじわじわと感じることができた。
この映画の存在を知った当初真っ先に沸いたのは、なぜフィンランド?という疑問だった。しかし作品を観ているうちに、その答えらしきものをじわじわと感じることができた。
それにもしこの作品が、日本のどこかの街で撮られたものであったなら、少々趣旨の違った作品になったのではないかと思う。
3人の日本人女性が、それぞれの理由でフィンランドに集まった。ヘルシンキで定食屋を営むサチエ(小林聡美)は、なかなか客の集まらない「かもめ食堂」で毎日皿を磨いている。彼女は『素朴だけど美味しいもの』をフィンランドの人に振る舞うためにここにやってきた。
サチエ:さて。朝一番白いごはんと一緒に食べたい焼き魚といえば?
ミドリ:・・・しゃけ?
サチエ:ほら!ね?日本の人もフィンランドの人も「しゃけ」好きなんですよ。
ミドリ:なるほどー。
サチエ:なーんて、たった今思いついたコジツケですけどね。
ミドリ:・・・ハハ。
 3人の中でフィンランド語を話せるのはサチエだけ。食堂を手伝うミドリ(片桐はいり)も、マサコ(もたいまさこ)も、接客では日本語を使う。実はこれこそが『かもめ食堂』という作品の要ではないかと思う。
3人の中でフィンランド語を話せるのはサチエだけ。食堂を手伝うミドリ(片桐はいり)も、マサコ(もたいまさこ)も、接客では日本語を使う。実はこれこそが『かもめ食堂』という作品の要ではないかと思う。
相手の話す言葉がわからなくても、自分の話せる言語に心を込める。そんな風に人と接することが出来たなら、意外とあっけなく心の通ったコミュニケーションが成立してしまうのかもしれない。物語に自然に入り込んでくる異国の空気は、登場人物たちの人となりをいっそう際立たせていた。
 そんな食堂の空気を、この作品が発する音がよく表している。
そんな食堂の空気を、この作品が発する音がよく表している。
食器が重なり合う音や、店内を行き来する靴の音。日常会話の音量の登場人物たちの会話。サチエの発する『Kiitos!(ありがとう)』も心地良く響く。(それは背後に控えているであろう撮影クルーの存在をも感じさせないのだ)
自分の名前を漢字で書いてもらい歓喜する日本アニメオタクのトンミ・ヒルトネン(豚身昼斗念)青年や、フィンランド発祥の「エアギター」の話題が登場するあたりは、なんとも今風の味付けであるし、なにより個性的なキャストが醸し出すちょっとした可笑しみは、もはや期待通りというべきだろう。
 彼女たちが作り、テーブルに出された “焼き魚” や ”おにぎり” がとても美味しそうに見えるのは、それが丁寧な所作の延長線上にあるからだと思う。(実際、映画を観た後で、誰かの作った料理を食べたくなり、定食屋へ駈け込んだほどだった)
彼女たちが作り、テーブルに出された “焼き魚” や ”おにぎり” がとても美味しそうに見えるのは、それが丁寧な所作の延長線上にあるからだと思う。(実際、映画を観た後で、誰かの作った料理を食べたくなり、定食屋へ駈け込んだほどだった)
ボトルにふきんを添えて飲み物を注ぐ。
キッチンの汚れは気付いた時に拭く。
菜ばしを丁寧に揃えて置く。
食器をきちんと整頓する。
そして、丁寧に人と接する。
『かもめ食堂』から丁寧な暮らしを感じれば、自分の生活がいかにそこから離れているかに気付くかもしれない。容易いようでなかなか叶わない “丁寧な暮らし” に価値をおける人なら、きっとこの作品に心地良さを感じるはずなのだ。
本日の1曲
クレイジーラブ / 井上陽水

——————————-
 『かもめ食堂』に続く、荻上直子監督作品『めがね』は本日公開
『かもめ食堂』に続く、荻上直子監督作品『めがね』は本日公開
▼『めがね』
脚本・監督:荻上直子
出演:小林聡美 市川実日子 加瀬亮 光石研 もたいまさこ 薬師丸ひろ子(「めがね」の友だち)
エンディングテーマ:大貫妙子
テアトルタイムズスクエア、銀座テアトルシネマ、シネセゾン渋谷ほか全国ロードショー
5月 28th, 2006 by taso
 「カンヌで失笑」「海外でR指定に認定」等と公開前から話題に事欠かない本作・・・要するに『ダ・ヴィンチ・コード』は大ヒットしている。
「カンヌで失笑」「海外でR指定に認定」等と公開前から話題に事欠かない本作・・・要するに『ダ・ヴィンチ・コード』は大ヒットしている。
高円寺から総武線に飛び乗り、吉祥寺の映画館へ。日曜の夜、映画館の螺旋階段に連なる列に一人で並んで開場を待つ。
小説を読んでいるだけに期待と不安が入り交じって・・・というのとは違う。原作を読んでしまったら映画を観ないとすっきりできない!
小説は上下巻(文庫なら3巻)の長編である。ほぼ一日に起きるストーリーにも関わらず、逃避に次ぐ逃避、更には国外脱出でめまぐるしい。この作品を2時間と少しにまとめようというのだから大変だ。
原作の膨大なプロットを短くする為に、効率よくストーリーを展開する必要がある。原作の中には多くの暗号が登場し、主人公を悩ませ続ける。この「謎解き」の連続が小説の面白みである。暗号を解くまでの試行錯誤や悶々とした時間が小説を魅力的なものにしていたが、なんだか映画ではやけにあっさりと暗号が解読されてゆく。悩んでいる時間も短縮しなくてはならないのだ。
しかしながら原作を読んでいない人はこのスピーディーな展開について来れるだろうか?敵や味方が瞬く間にすり変わり、史実を交えた抽象的な会話が続く。予備知識がない人は、凶弾に倒れ画面に大写しになった人物が果たして誰なのかわからないまま”置いてけぼり”をくらう可能性がある。
方や、原作を読んでいる人は、その省略の脚本を楽しむこともできる。進行してゆく映像を眺め、もう一度小説の筋書きを思い起こすことができる。
人気小説の映画化において、大抵の人が『原作の方が面白い』と口を揃える。本作を観た感想を正直に述べるならば『スッキリした!』ということになる。
数年ぶりに映画館に行った。それにしても映画館の予告はあんなに長かっただろうか?20分程延々と予告が続き、予告が終わる頃には皆ポップコーンを食べ終えているようだった。そして1000円で観ることのできるバースデー割引があることを初めて知った。
本日の1曲
Desire / Zwan

——————————-
>>connection archive >>
5/16 『話題の書『ダ・ヴィンチ・コード』』
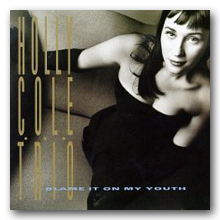












 この映画の存在を知った当初真っ先に沸いたのは、なぜフィンランド?という疑問だった。しかし作品を観ているうちに、その答えらしきものをじわじわと感じることができた。
この映画の存在を知った当初真っ先に沸いたのは、なぜフィンランド?という疑問だった。しかし作品を観ているうちに、その答えらしきものをじわじわと感じることができた。 3人の中でフィンランド語を話せるのはサチエだけ。食堂を手伝うミドリ(片桐はいり)も、マサコ(もたいまさこ)も、接客では日本語を使う。実はこれこそが『かもめ食堂』という作品の要ではないかと思う。
3人の中でフィンランド語を話せるのはサチエだけ。食堂を手伝うミドリ(片桐はいり)も、マサコ(もたいまさこ)も、接客では日本語を使う。実はこれこそが『かもめ食堂』という作品の要ではないかと思う。 そんな食堂の空気を、この作品が発する音がよく表している。
そんな食堂の空気を、この作品が発する音がよく表している。 彼女たちが作り、テーブルに出された “焼き魚” や ”おにぎり” がとても美味しそうに見えるのは、それが丁寧な所作の延長線上にあるからだと思う。(実際、映画を観た後で、誰かの作った料理を食べたくなり、定食屋へ駈け込んだほどだった)
彼女たちが作り、テーブルに出された “焼き魚” や ”おにぎり” がとても美味しそうに見えるのは、それが丁寧な所作の延長線上にあるからだと思う。(実際、映画を観た後で、誰かの作った料理を食べたくなり、定食屋へ駈け込んだほどだった)
 『かもめ食堂』に続く、荻上直子監督作品『めがね』は本日公開
『かもめ食堂』に続く、荻上直子監督作品『めがね』は本日公開 ソフィア・コッポラはこれまでにも未熟な精神の揺らぎを描き続けてきた。ティーンエイジャーや孤独なものへのこだわりは彼女のあらゆる表現活動のテーマであり続けている。
ソフィア・コッポラはこれまでにも未熟な精神の揺らぎを描き続けてきた。ティーンエイジャーや孤独なものへのこだわりは彼女のあらゆる表現活動のテーマであり続けている。 時代の主流であったクラシック音楽ではなく、ロックミュージックを用い、色彩や質感へもこだわる。青春グラフィティー、ガーリー、ロマンティック。ソフィアのクリエーションのキーワードがちりばめられ、そのさじ加減がなんともソフィア的で期待を裏切らない。
時代の主流であったクラシック音楽ではなく、ロックミュージックを用い、色彩や質感へもこだわる。青春グラフィティー、ガーリー、ロマンティック。ソフィアのクリエーションのキーワードがちりばめられ、そのさじ加減がなんともソフィア的で期待を裏切らない。 散らかった部屋や、食べ残しのぐちゃぐちゃになったケーキのカットはフォトグラファーの感覚で描かれている。ベルサイユ宮殿での壮大なロケーションを含め、作品全体が写真を撮るための壮大な計画のように完璧だった。
散らかった部屋や、食べ残しのぐちゃぐちゃになったケーキのカットはフォトグラファーの感覚で描かれている。ベルサイユ宮殿での壮大なロケーションを含め、作品全体が写真を撮るための壮大な計画のように完璧だった。 アートを学ぶ学生が思い描いた夢のような原案を莫大な費用と関係者の協力によって作り上げた、例えるならこういう感覚に近い。
アートを学ぶ学生が思い描いた夢のような原案を莫大な費用と関係者の協力によって作り上げた、例えるならこういう感覚に近い。
 映画『
映画『 デジタルビデオの映像をベースに書き起こされたイメージは、いびつで不安定だ。カメラの揺れをそのままに描く為、画面は多方向に揺らぎ、登場人物の顔や背景も変化し続ける。
デジタルビデオの映像をベースに書き起こされたイメージは、いびつで不安定だ。カメラの揺れをそのままに描く為、画面は多方向に揺らぎ、登場人物の顔や背景も変化し続ける。 街を彷徨い歩く若者に出くわした人間たちはやや一方的に自己流の哲学を語っていく。
街を彷徨い歩く若者に出くわした人間たちはやや一方的に自己流の哲学を語っていく。 会話の途中で人間は雲に変化したり、興奮した男の顔は徐々に赤くなっていく。それはアニメーションだから為し得る演出で、アニメーションの写実的な側面とマンガ的な側面を融合させた面白いシーンになっている。
会話の途中で人間は雲に変化したり、興奮した男の顔は徐々に赤くなっていく。それはアニメーションだから為し得る演出で、アニメーションの写実的な側面とマンガ的な側面を融合させた面白いシーンになっている。


 『太陽を盗んだ男』を最初に観たのは大学時代だった。その作品を知ってから観るまでに少し時間があった。深夜にテレビで放映されていたのを観て、なんだかただ者ではない雰囲気にチャンネルを変えた。
『太陽を盗んだ男』を最初に観たのは大学時代だった。その作品を知ってから観るまでに少し時間があった。深夜にテレビで放映されていたのを観て、なんだかただ者ではない雰囲気にチャンネルを変えた。 そして彼は原爆を作ることに成功する。実験室と化した自宅のテレビからは野球のナイター中継が流れる。作業の合間に鼻歌を歌い、ナイターを眺める。テレビの中継がいつもいいところで終わってしまうのが彼の不満だった。
そして彼は原爆を作ることに成功する。実験室と化した自宅のテレビからは野球のナイター中継が流れる。作業の合間に鼻歌を歌い、ナイターを眺める。テレビの中継がいつもいいところで終わってしまうのが彼の不満だった。







