『荒野へ』
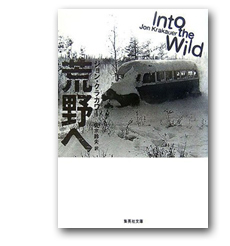
ジョン・クラカワー/著
佐宗 鈴夫/訳
¥700(集英社文庫)
1992年の4月、東海岸の裕福な家庭に育ったひとりの若者が、ヒッチハイクでアラスカまでやってきて、マッキンレー山の北の荒野に単身徒歩で分け入っていった。4か月後、彼の腐乱死体がヘラジカを追っていたハンターの一団に発見された。
全米でベストセラーとなったノンフィクション、『荒野へ』は、こんな書き出しから始まっている。友人と入った書店で、とにかくすごいからと薦められ手にとったにしろ、興味を持たずにいられない何かがあった。
彼はなぜ、不自由のない暮らしを捨て、わざわざアラスカにまで行って無惨な死に方をしなくてはならなかったのか?
クリストファー・J・マッカンドレスに仕事以上の興味を持ったクラカワー氏の緻密な取材行為のおかげで、私達は「アラスカで餓死した青年」の個性を感じられるようになる。
裕福な家庭に育った青年が、裕福であるがゆえに自分の境遇に満足できなかったとしたら。若者は感化されやすく物事に傾倒しやすい。先人の偉大な書物に傾倒するあまり、今日の文明に違和感を感じてしまう若者がいたとしても不思議ではない。
しかし、マッカンドレスの死が全米に知れ渡ると、少なくない人々が不快感を口にしたそうだ。日本でも時々ある、危険な地域に足を踏み入れ命を落とした若者を語るときと同じように。そして当然のごとく、彼らは一部の人々に英雄のように崇められたりもする。
マッカンドレスがアラスカに向かった時、欲求だけに突き動かされ、興奮状態で地に足がつかず、冷静さを欠いていたのかもしれない。若さは時にそういう事態をもたらす。
けれども、強い意思なくして行動を起こすとはできない。彼は、強い意思をもってアラスカに向かい、いくつかのミスのせいで結果的に命を落とすことになってしまったのだ。
彼はカメラとノートを持ち、人生を変える旅の記録を残していた。そのおかげで死の直前をどのように迎えたかのかも、私達は推測することができる。
本著は、死後に論争を巻き起こした青年が、ただの青年だった頃の話だ。そして、ある人物について深く掘り下げ、事実、もしくは事実に近い物語を提示する作家という職業の素晴らしさを感じさせる作品でもあった。
マッカンドレスは、地図に記載されていない地域を放浪したがっていたという。
しかし彼がアラスカを訪れた1992年にはアラスカに地図上の空白地が残されていなかった。そこで彼は地図を捨て、彼の頭に未知の大地を残した。彼にとっては、簡単ではないということがなによりも重要だった。
毎日、テレビをつけているだけでいくつものニュースが読み上げられていく。この本を読んだあとは、それがいっそう早く感じられた。
我々はニュースの主人公達の人生について少しでも考えを巡らせるべきなのだ。
本日の1曲
Sæglópur / Sigur Rós
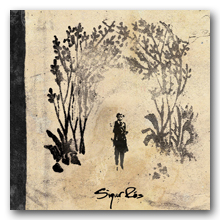
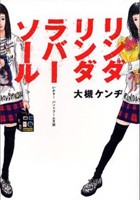 ボンクラ青年の恋
ボンクラ青年の恋 村上春樹 『ニューヨーク炭鉱の悲劇』
村上春樹 『ニューヨーク炭鉱の悲劇』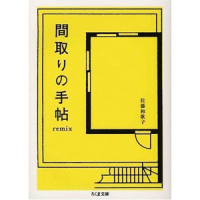 『間取りの手帖 remix』
『間取りの手帖 remix』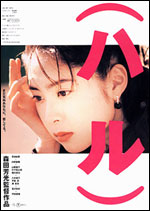





わたしも読みました。
読んだあとは、もう、衝撃だった。
結局、彼の命を奪った
いくつかのミスの内容にいたる記述は
時間を忘れて読んでしまいました。
個人的には、作者の若いころの、
氷山を登るシーンを何回も読み直しました。
>ちんみんさん
氷山の回想シーンは、すごく迫力があったけど、山の中の孤独を想像したら堪らない気持ちになりました。
自分の知らない世界に圧倒された感じ。
良い本を紹介してくれてありがとう!
ちんみんさんはいつもたくさん本を読んでいて感心してしまいます。また本屋に立ち寄ろうね。