映画『アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生』

アニー・リーボヴィッツとの撮影を終えたわずか数時間後にジョン・レノンは暗殺され、その写真は広く世に知られることになった。胎児のように体を丸め、全裸でヨーコに抱き着く彼のポートレイトを見ていると、そんな皮肉な運命が信じられなくなる。
『アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生』は、女流写真家アニー・リーボヴィッツの半生を描いたドキュメンタリームービーである。ハリウッドスターや世界有数のモード誌の編集長、あのヒラリー・クリントンまでが登場し、アニー自身とアニーの作品の魅力を興奮した表情で話す。
かの有名なRolling Stone誌にカメラマンとして在籍していた間、アニーはロックバンドのツアーに同行し、ステージ写真のほか、バックステージや滞在先のホテルなどでオフショットを撮るようになる。
日常的な風景と人物との間にも、思わず記録せずにはいられない瞬間がやってくる時がある。多くの人はレンズを向けられたその瞬間に他者を意識してしまう。あるロックスターは「(行動を共にしてから数日後には)彼女の存在が気にならなくなった」と語った。
それはカメラのレンズを介した両者がイコールに近いエネルギーを発する時に起こりうる現象で、エネルギーが多くても少なくても、それは叶わない気がする。たとえ優れた表現者を前にしても、彼女にはレンズの向こうの被写体とイコールになれるエネルギーがある。だからこそ存在を「消す」ことができたのではないだろうか、と。

__ 個性的で表情豊かなモチーフが目の前に用意されていたら、シャッターを切りさえすれば印象的な写真が撮れる? それなら誰がシャッターを切っても同じだということにならない?
以前ある友人氏は不思議そうに言った。
確かにフォトジェニックな(絵になる)モチーフや人物は写真を魅力的なものにする。しかし写真は一人の人間の限られた視界そのものであり、一枚の写真にはそこに存在することを選択した個人の意思が反映されているはずなのだ。写真を見るとき、その対象にレンズを向けた人間のアイデンティティを感じないだろうか。同じ場所に立っても同じ視界を持つ人間はいないはずで、瞬間を記録したい衝動がシャッターボタンを押させるのだから。
アニーは幼い頃から転居の多い生活をしていたみたいだった。景色を眺めながら次の土地へ向かう彼女にとって、車の窓枠は世界を切り取る「フレーム」だった。車を運転しながらインタビューに答えるアニーは、『私はいつも写真の構図のことばかり考えている』と言った。
確かに、毎日デッサンばかり描いていた浪人生の頃は、どこにいて何をしていても、物質の光の反射や、影や、パースペクティブが気になって仕方がなかった。親指と人差し指で作ったLの字を目の前にかざし、視界をトリミングしたりもした。
それはおそらく、「表現者の目」を持っているがゆえの癖のようなものだ。表現者は常に見つめ続けている。何かを表現するためには、物事を見つめなくてはならない。しかし表現者でなくなってしまえば、その癖もいつしか消えてしまう。
髪を振り乱しながらポートレイトを撮影するアニーの姿は喜びに溢れ、野性を感じさせもした。
映画館を出ると、久し振りにモノクロのポートレイトを撮りたくなった。それと同時に、今の自分は何に愛を感じてシャッターを切れるのだろうかとぼんやり考えもした。
本日の1曲
Simple Song / Richard Ashcroft

——————————-
▼『アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生』
http://annie.gyao.jp/

監督・製作:バーバラ・リーボヴィッツ
2007年/83分/カラー/アメリカ
Photographsc2007 by Annie Leibovitz
2008年2月16日(土)より シネマGAGA!、
シネカノン有楽町2丁目他 全国順次ロードショー
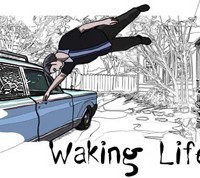 混乱と踊るサルサ『Waking Life』
混乱と踊るサルサ『Waking Life』 映画(ハル)
映画(ハル) 世界一有名なティーンエイジャー 『マリー・アントワネット』
世界一有名なティーンエイジャー 『マリー・アントワネット』





0 Responses to “映画『アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生』”