いいわけ癖
あるミュージシャンのエッセイを読んだ。1年間の雑誌連載が終了して半年後に書籍版が刊行されたのだ。ミュージシャンらしい着眼点に感心し、日々の暮らしのエピソードは面白く書かれている。雑誌に連載されていた頃からその文章のファンであった。
ページの欄外には”現在の”彼のコメントがついている。そのスペースで彼は連載当時を振り返っている。『この文章は無理矢理でしたね』とか、『論点まとまってないですね』とか、どちらかというと後ろ向きな発言が多い。『よく書けた!』というものはひとつもない。
(この人、自分と似てるな)と思った。それを言わなければ、落ち度なんてわからないのに。
卒業制作でアニメーションを作った。どう考えても間に合わないスケジュールにあくせくしているうちに提出期限は訪れた。手を加えたいところはいくらでもあるが時間と技術が追いつかない。結局「半端な」作品を提出しなくてはならなかった。
講評の当日、教室では学生達がそれぞれの作品の前に立ち、自分の作品について説明する。計画性のあるほとんどの生徒は完成度の高い作品を提出し、立派なプレゼンテーションを繰り広げる。その様子を後方から眺めていると、真冬なのに冷や汗が出てくる。
遂に順番がまわってきてしまった。頭は混乱し、気付けば言い訳を放出していた。
『背景も動かしたかったんですケド (できませんでした)』
『もう一作品作る予定だったんですケド (時間がありませんでした)』
『こういう効果を出したかったんですケド (失敗してしまいました)』
突っ込まれる前にアラを暴露した。学生生活の集大成のイベントであるのに、未完成の作品を提出してしまったのだ。恥ずかしいやら、情けないやら、動揺がおさまらない。その時自分の作品に対する自信はすっかり忘れていた。
作品の講評は二人の教授とそのゼミを専攻する全ての学生の前で行われた。所属していた空間演出デザイン科は立体作品が多かった。大型作品を展示する学生も多く、制作シーズンの校舎はそこら中が工場と化している。皆が真冬の校舎に遅くまで残って制作を続けていた。彼等はお互いの制作過程を知っている「仲間」に見えた。
制作過程にもタイプがある。構想段階から教授にみっちり指導を受ける人や、簡単なチェックを受けただけで最後まで自分の殻に閉じこもる人もいる。明らかに後者に属する自分の作品は、完成まで誰の目にも触れていなかった。皆が開放的に制作に取り組んでいる間、自室でデスクトップムービーを作っていたのだから。余計に奇異な視線が注がれているような気になる。
一人の教授は作品を観て、『上村一夫の世界観だね。』と言った。よく言えば”荒削り”の作風は、決してマイナスにだけ作用するものではなかったのだ。
硬直して突っ立っている自分に教授はこうも言った。『自分が思っている欠点は、口にしなければ気付かないものだよ。』
その言葉は忘れられない言葉となった。理想に辿り着けなくても、自分の作品を否定する必要などなかったのだ。
本日の1曲
Kissing My Love / odani misako・ta-ta

 想像力。
想像力。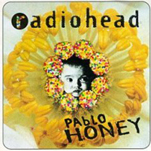 カレッジ・デイズ
カレッジ・デイズ 酒場人間模様
酒場人間模様 おじいちゃんの幸せなアトリエ
おじいちゃんの幸せなアトリエ





0 Responses to “いいわけ癖”