『コインロッカー・ベイビーズ』

村上龍/著
¥490(講談社文庫)
改札の向こうにあるコインロッカーには「コインロッカーに入れてはいけないもの」という注意書きが掲げられていた。ある日、何気なく目を遣ると、そのリストの中に「死体」があることに気が付いた。
それは他の文言と並列に表記されているのは少し違和感があった。
その日以来、コインロッカーを見るたびに注意書きが気になるようになってしまった。そしてこれまで目にしたほとんどのコインロッカーには、やっぱり「死体」という文字があった。
コインロッカーはブラックボックスなのだ。誰が何を預けたかは、本人以外にはわからない。
コインロッカーは壁や柱と同じなのだ。人々はその中に何が入っているかなんて考えないし、そんなことに興味もない。扉が堅く閉じられたままでも暫く誰にも気付かれないだろう。
キクとハシはそんなコインロッカーで発見された。それぞれの母親によって、生後まもなく置き去りにされた二人の孤児は、乳児院で兄弟のように育てられた。キクは気の弱いハシをいつも守ってやった。
母を捜すため東京にやってきたハシは男娼となり、「薬島」と呼ばれるスラムに住み着いた。後にハシは、才能を見出だされ歌手としてデビューする。コインロッカーで生まれたといういわくつきの出生が瞬く間に彼を有名にした。
一方、ハシを追って東京にやってきたキクは、「東京を真っ白にする」恐ろしい物質を手に入れようとしていた。キクは世界を憎み、復讐のためならどんな危険でも冒してしまう。凶暴な魂で復讐を試みるキクと、次第に自分をコントロールし始めるハシ。
『コインロッカー・ベイビーズ』を初めて読んだのは大学生の時だった。読むそばから、言葉は次々に映像に転換されていった。喩えるなら、頁から剥がれた活字が鮮やかなインクになって、頭の上にどろどろ垂れてくるような感じがした。句読点の少ない夢想的な描写の連続は、幻覚を見ているかのような気分にさせた。
その濃密な文章で、むせ返る空気や生き物の血の匂いが生々しく迫ってくる気がする。キクとハシ以外にも、鰐(ワニ)を飼う少女「アネモネ」や、ハシを発掘した男色の音楽ディレクター「ミスターD」など、独特の人物像が物語の世界観をより強固なものにしていた。
何をしていてもまとわりついて離れない不幸を跳ね返す方法はあるんだろうか。動かなくてはならないとしたら、何をどうすればいいのだろう。物語の中で動き回るキクとハシを見ているうちに、自分が最善と信じるやり方は愛する人を幸せにするだろうかと、自問するようになった。
「じゃ、俺はもう飛ばなきゃ」
キクは立ち上がった。隠しておいたグラスファイバーポールを取り出す。うわあきれい、レーザー光線みたい、銀色の半透明の長い棒を見てアネモネが言った。うまく跳んでね、写真とるから。
上巻でキクが薬島を囲む鉄条網を棒高跳びで跳び越えるシーンがある。この作品を思い出す時はいつも、半円の弧を描いて真夜中の空に舞うキクの姿が目に浮かぶ。
都心の夜の通りを歩いていると、高い鉄の柵の向こうの茂みが見えた。今にも目の前をキクが飛び越えていくんじゃないかという錯覚が襲う。そんな時は、きらきらと弧を描くポールの先端に、細く長い手足で絡みつくキクが見えるような気がしてしまう。
本日の1曲
KICK IT OUT / BOOM BOOM SATELLITES

 村上春樹 『ニューヨーク炭鉱の悲劇』
村上春樹 『ニューヨーク炭鉱の悲劇』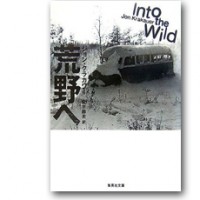 『荒野へ』
『荒野へ』 リリー・フランキー 『東京タワー』
リリー・フランキー 『東京タワー』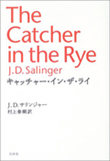 J.D.サリンジャー 『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
J.D.サリンジャー 『キャッチャー・イン・ザ・ライ』





0 Responses to “『コインロッカー・ベイビーズ』”